いきなり例文から入ります。
日本語とは面白いもので、語尾を変えると印象が変わります。
または、文末表現を変えると印象が変わります。
イケダハヤト氏が『武器として書く技術』(中経出版)の中で指摘しています。
唐木元氏も『新しい文章力の教室』(インプレス)の中で指摘しています。
私はいま意図的に語尾・文末表現を同じようにしています。
「ます」で終わるようにしています。
イケダハヤト氏は「同じ語尾が続くと単調で眠くなります」と言います。
さて、くどいようですが、文末を「ます」で終わらせる文章を並べました。
イケダハヤト氏が言うように「単調」かもしれません。
試しに上記の語尾・文末を書き換えてみましょう。
日本語とは面白いもので、語尾を変えると印象が変わります。
文末表現を変えると印象が変わる、と言い換えてもいいでしょう。
イケダハヤト氏が『武器として書く技術』(中経出版)の中で指摘していることです。
唐木元氏も『新しい文章力の教室』(インプレス)の中で指摘していました。
私はいま意図的に語尾・文末表現を同じようにしています。
「ます」で終わるようにしました。
イケダハヤト氏に言わせれば、「同じ語尾が続くと単調で眠くなる」とのことです。
あまり出来は良くありませんが、少しは単調さが薄まったでしょうか。
日本語の文章では、語尾・文末を変化させることによって、活字に躍動感が生まれます。
私はまだ熟達していませんが、文章のプロは文末表現に気を配ることを怠りません。
※ちなみに上の3行の文末表現も「しょうか」「ます」「ません」などと変えてみました。
以前、似たようなことをツイッターでリツイートしたことがあります。
業界紙で記者稼業をしていたとき、文末が同じ表現にならないよう指摘されたもの。リズムを大切にするため、語尾の表現は繰り返さないようにしたい。体言止めも3回以上連続で繰り返すと、くどくなる。
上記の文章の文末は、
・もの
・したい
・なる
―と変えてみた。#文章修行 #文末表現 #記事 https://t.co/fh33yud07O— Communication Skills Labo (@hau77800) January 20, 2019
文章の語尾・文末表現が重複するようなら、文章自体が単調になります。
一方で文章の語尾・文末表現に変化をつけるなら、文章に躍動感が生まれるでしょう。
学生にありがちな文末表現
学生時代、人文学部で学んでいた友人の文章の特徴はよく覚えています。
とにかく文末表現に「である」が多いのです。
例えば、以下のような文章を挙げてみます。
NTTの研究開発の人材は35歳になるまでに3割がGAFAなどに引き抜かれてしまうようである。
GAFAとは、グーグル(Google)、アップル(Apple)、フェイスブック(Facebook)、アマゾン(Amazon)の頭文字である。
検索、スマートフォン、SNS、EC(電子商取引)で圧倒的なシェアを持ち、市場の土台を支配しているグローバルIT企業が、日本企業から若くて優秀な人材を次々と引き抜いているのである。
NTTの研究開発職の初任給は大卒が21万5060円、修士課程が23万7870円だが、世界的に人材の獲得競争が厳しくなっており、GAFAなどは新卒でも優秀なら年収数千万円で採用するとのことである。
「日本型雇用が日本人を幸福にした」というのは幻想であり、真っ赤なウソだったのである。
文章は、橘玲著『働き方2.0 vs 4.0 不条理な会社人生から自由になれる』(PHP研究所)にある内容を参考にしました。
「である」と断定すれば、文章に力強い権威性が生まれます。
ただし、多用すると逆効果です。
「である」という断定の表現は、ここぞというときに使ってこそ効果が生まれます。
友人は当時、知ってか知らずか、文章に説得力を持たせたくて「である」を多用したに違いありません。
けれども文章の文末が常に「である」だと、くどくなります。
「である」で、ふとある文学作品の一節が思い浮かびました。
文豪・夏目漱石の『吾輩(わがはい)は猫である』です。
冒頭の数行だけを読むだけで、夏目漱石がいかに文末表現に工夫を凝らしていたかが分かります。
中学生レベルでよければ、品詞分解をしてみます。
吾輩は猫である。
→断定の助動詞「だ」の連用形+補助動詞「ある」の終止形
名前はまだ無い。
→形容詞「無い」の終止形
どこで生れたかとんと見当けんとうがつかぬ。
→動詞「つく」の未然形+打消しの助動詞「ぬ」の終止形
何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
→補助動詞「いる」の終止形
吾輩はここで始めて人間というものを見た。
→動詞「見る」の連用形+過去の助動詞「た」の終止形
しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪どうあくな種族であったそうだ。
→伝聞の助動詞「そうだ」の終止形
この書生というのは時々我々を捕つかまえて煮にて食うという話である。
→断定の助動詞「だ」の連用形+補助動詞「ある」の終止形
しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。
→過去の助動詞「た」の終止形
ただ彼の掌てのひらに載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。
→断定の助動詞「だ」の連用形+補助動詞「ある」の終止形
掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始であろう。
→補助動詞「ある」の未然形+推量の助動詞「う」の終止形
この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。
→補助動詞「いる」の終止形
こうしてみると、文末表現が上手に散らされています。
同一表現による重複を、意図的に避けているかのようです。
実際、夏目漱石は意識して重複を避けたに違いありません。
ナタリー式トレーニングで知られる唐木元著『新しい文章力の教室』(インプレス)では、「時制を混在させて推進力を出す」といった上級レベルの文章術を紹介しています。
例を挙げます。
会場に詰めかけたドリカムファンは、じっと吉田美和の歌声に耳を澄ませた。
中村正人の6弦ベースが、歌声に合わせて低音を響かせた。
ファンは、切ない恋の歌に心の中でウォンウォン泣いた。
一転して「何度でも」の楽曲が始まると、ファンは腕を振り上げて喜んだ。
ドリカムファンには申し訳ありませんが、いま適当に文章を作りました。
過去形ばかりで単調な文末です。
これを細工してみます。
会場に詰めかけたドリカムファンは、じっと吉田美和の歌声に耳を澄ませる。
中村正人の6弦ベースが、歌声に合わせて低音を響かせた。
ファンは、切ない恋の歌に心の中でウォンウォン泣きじゃくる。
一転して「何度でも」の楽曲が始まると、ファンは腕を振り上げて喜んだ。
少しは違いが出たでしょうか。
過去の時系列の中に「済ませる」「泣きじゃくる」といった現在形の表現を取り混ぜてみました。
うまくいけば、文章に臨場感をもたらすことができます。
過去の出来事を現在形で書いた秀逸な文章があります。
たまたまツイッターで流れてきた情報ですが、びっくりするほど使い方がうまくて参考になります。
ついさっきの出来事を、電車で書きました。昭和のはずれから来たようなおじいさんとのお話。
6月3日の歯医者帰り|夏生さえり @N908Sa|note(ノート) https://t.co/2SSrgiZbPR
— さえりぐ (@saeligood) June 3, 2019
たとえば、こんな文章があります。
周りを歩く人たちは、わたしたちなど目にも入らないように足早に通り過ぎる。途中、迷惑そうにこちらをみる男の子もいた。すみませんね、ここら一帯が昭和のようで。
暑くもなく、寒くもない6月の晴れの日。
わずかに交わって、すぐに別れた。
過去の時系列の話の中に、さりげなく現在形を取り入れています。
文末の表現も多彩です。
唐木元氏は「多用は禁物」としつつも、時系列の混乱を招かない範囲で、過去の出来事を現在形で書くことをバリエーションの一つとして取り入れることを勧めます。
書き手の意識が「過去の時点から見た現在」にあれば、過去の出来事を現在形で書いても成り立つのです。 (略)
同じことは未来についてもいえます。次の例文で「未来の時点から見た現在」の表現がもたらす余韻を味わってみてください。
参照:唐木元著『新しい文章力の教室』
「未来の時点から見た現在」の表現の違いを知るため、二つの例文を載せます。
北海道四季劇場のファイナル公演となるディズニーミュージカル「リトルマーメイド」。観客は感動のフィナーレを目にするだろう。
未来の出来事を推定するような書き方です。
対して下記の文章は、いままさにそこで起こりつつあるような迫力をもたらします。
北海道四季劇場のファイナル公演となるディズニーミュージカル「リトルマーメイド」。観客は感動のフィナーレを目にする。
まとめ
冒頭でお粗末な例文を並べましたが、語尾や文末表現を変えるだけで、文章に躍動感が生まれます。
重複だらけの文末には、芸がありません。
語尾が重複だらけだと、読む方も文章に「しつこさ」を味わうでしょう。
イケダハヤト氏は、同じ語尾が続いた文章を、残念な人の文章と指摘します。
残念な人の文章とならないため、私たちはできる限り語尾・文末表現のバリエーションを増やしたいものです。
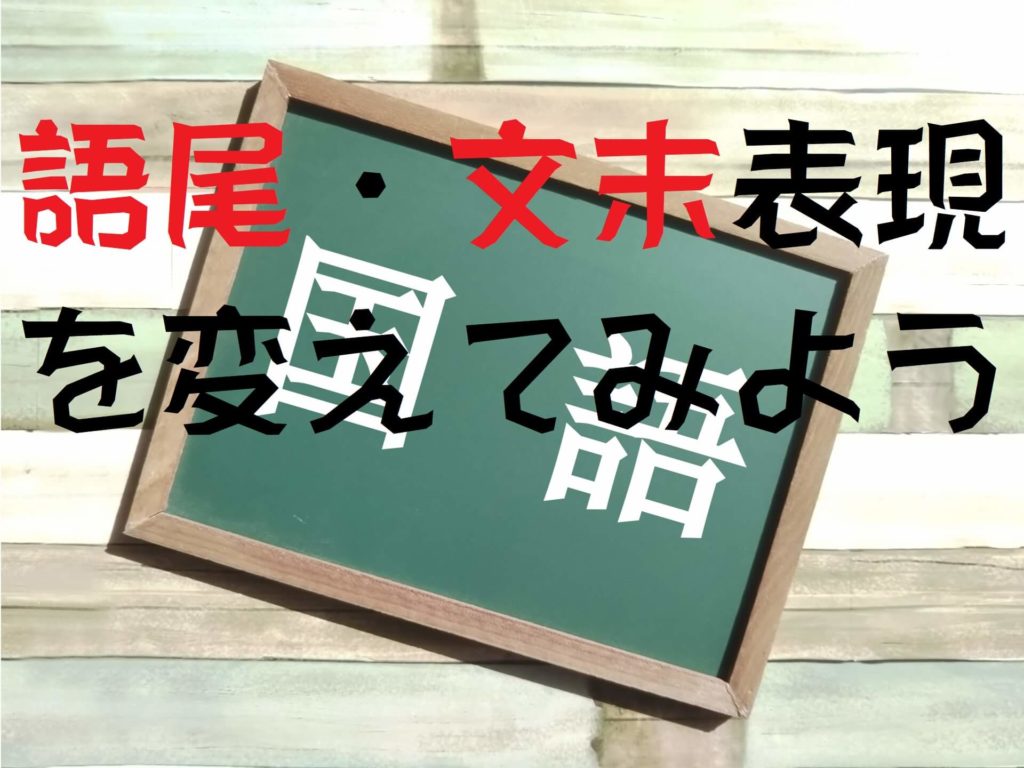
















吾輩は猫である。
名前はまだ無い。
どこで生れたかとんと見当けんとうがつかぬ。
何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
吾輩はここで始めて人間というものを見た。
しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪どうあくな種族であったそうだ。
この書生というのは時々我々を捕つかまえて煮にて食うという話である。
しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。
ただ彼の掌てのひらに載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。
掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始(みはじめ)であろう。
この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。